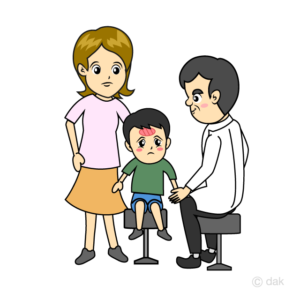発達障害者支援法には、「発達障害」は脳機能の障害(第2条第1項)と断定する表現となっています。具体的に脳のどの部分がどのような原因でどの程度正常とかけ離れた状態になっているのかという説明を一切することなく、単にその一言だけでいかにも、医学的、学術的に聞こえてしまいます。

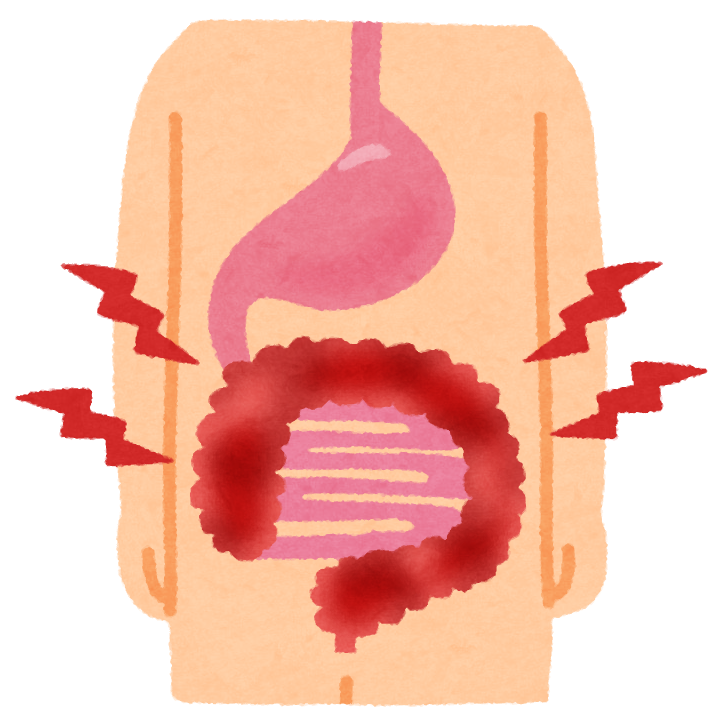
脳がうまく機能しない「状態」はありますが、原因はさまざまです。特定の遺伝子が先天的に欠損しているのかもしれません。単に睡眠不足かもしれません。脳が働くために必要な栄養が不足しているのかもしれません。あるいは脳自体に問題がなくても、先天的に腸に問題があって、脳の働きに必要な特定の栄養が身体に吸収されないのかもしれません。
脳機能だと断定するのであれば、その原因はさておき、少なくとも脳のどこの部位がどう機能していないのか最低限説明するべきだと思うのです。それができないのであれば、断定的な表現は避けるべきです。

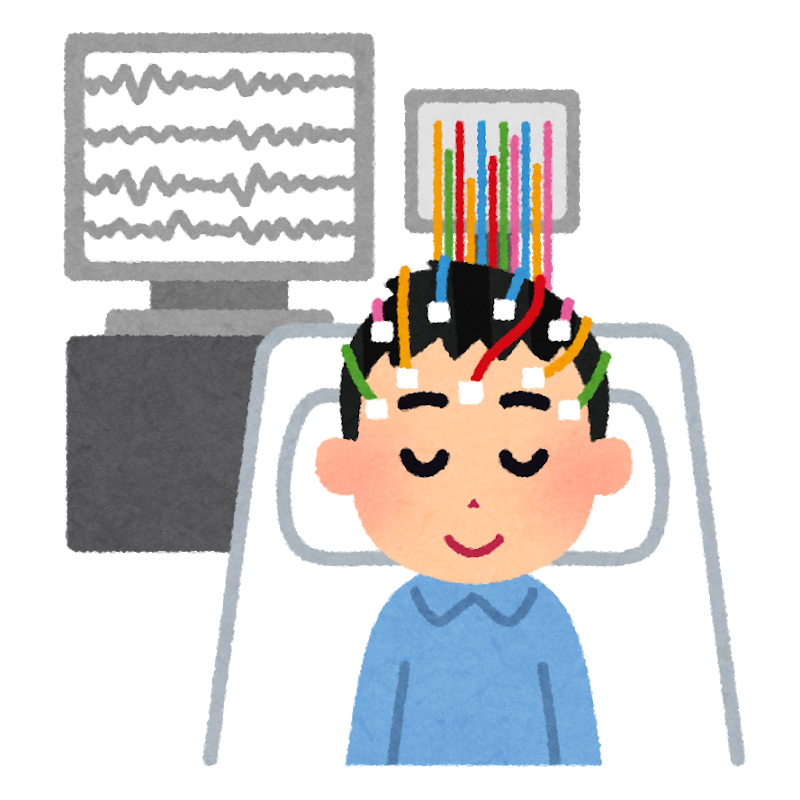
ここで大きな疑問が出てきます。専門家はどのようにして「脳機能障害」と特定するのでしょうか。素人考えだと、MRIや脳波検査、光ポトグラフィ等を用いて脳の状態を確認し、特定の部位が正常な状態から明らかに外れていることを根拠にして、なおかつそれが後天的に生じたものではないことを証明できてはじめて確定診断できるものだと思えます。
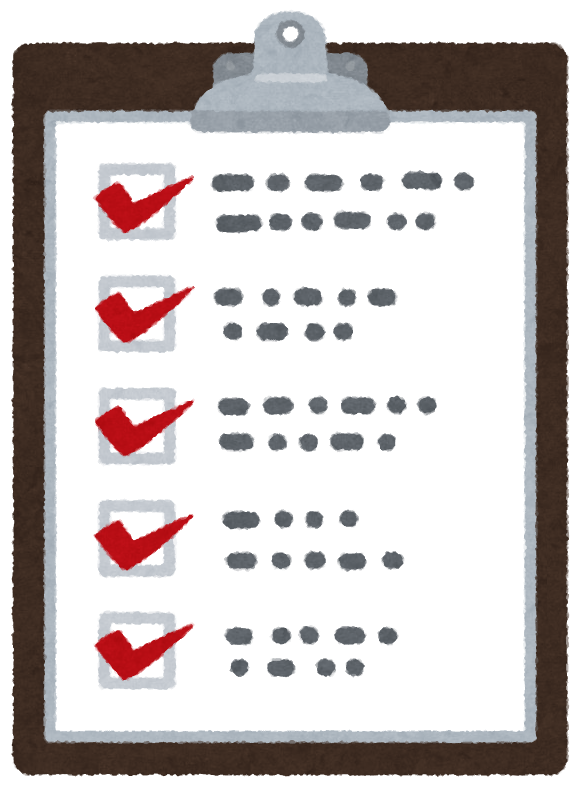
しかし、実際に診断の手法として使われているのは、「問診」なのです。診断基準(チェックリスト)に基づいた問診を通して、医師は患者の状態や背景を探っていきます。そして、最終的に医師の主観に基づいて診断ができるのです。
国立精神・神経医療研究センターによると、ADHDにおいて「病気や障害の指標となる決定的なバイオマーカーが未だに発見されておらず、その診断においては、経験豊かな専門家による主観的な行動観察にもっぱら頼らずを得ない現状があります」と説明されています。

行動観察というのは原因の特定ではなく、あくまでその結果として表に出てきている症状を観察しているにすぎず、それが脳機能障害から出た症状なのか、それ以外の理由で生じた結果なのか、区別することができるのでしょうか。
脳機能障害が実際にあったとしても、それが先天的な原因か後天的な原因かをどうやって問診だけで区別できるのでしょうか。このような疑問を抱きつつも、現実は医師の問診と主観により診断され続けているのです。そして、子どもに向精神薬が処方されるようになってしまったのです。
(つづく)
参考文献:「発達障害バブルの真相」米田倫康 著 萬書房